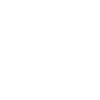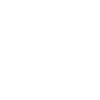
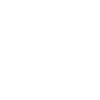





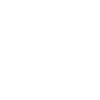


今まで備前焼を制作していて、
その中で緋襷(ひだすき)という模様が面白いと思い、
それを生かした作品を作りたいと考えたからです。
今まで備前焼を制作していて、その中で緋襷(ひだすき)という模様が面白いと思い、それを生かした作品を作りたいと考えたからです。


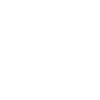


岡山県の備前市で主に生産されており、
日本六古窯(ろっこよう)という6つの古い窯の1つです。
皆さんのよく使っている食器は表面がツルツルしていますが、
それは釉薬がかかっているからであり、
備前焼は釉薬をかけずに焼きしめることで
ざらざらしているのが大きな特徴です。
岡山県の備前市で主に生産されており、日本六古窯(ろっこよう)という6つの古い窯の1つです。
皆さんのよく使っている食器は表面がツルツルしていますが、それは釉薬がかかっているからであり、備前焼は釉薬をかけずに焼きしめることでざらざらしているのが大きな特徴です。


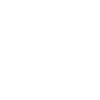


緋襷は藁をくっつけて焼くことで、藁がついていた部分に赤い模様ができます。
側面にぴったりとつけて焼くことが必要なのですが、その工程が非常に困難です。
そこで、作品より一回り大きな作品を作り、
その中に入れて焼くことで藁が上手くくっつくような焼き方の工夫をしました。
緋襷は藁をくっつけて焼くことで、藁がついていた部分に赤い模様ができます。
側面にぴったりとつけて焼くことが必要なのですが、その工程が非常に困難です。
そこで、作品より一回り大きな作品を作り、その中に入れて焼くことで藁が上手くくっつくような焼き方の工夫をしました。



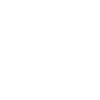


作品である焼き物を作る際に、
紐づくりという粘土を紐のようにして下から回転するように
積み上げる技法で作りました。
それが形にそのまま反映されて竜巻のような形になっているところが魅力です。
作品である焼き物を作る際に、紐づくりという粘土を紐のようにして下から回転するように積み上げる技法で作りました。
それが形にそのまま反映されて竜巻のような形になっているところが魅力です。


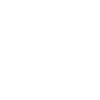


私の作品は大きいため、ヒビが入ったり、
へたったりすることが初めは多発していました。
しかし、何度も作り直すことで、
乾燥状態の管理や手の動きなどが徐々に慣れていき、
失敗せずにできるようになったときに成長を感じました。
私の作品は大きいため、ヒビが入ったり、へたったりすることが初めは多発していました。
しかし、何度も作り直すことで、乾燥状態の管理や手の動きなどが徐々に慣れていき、失敗せずにできるようになったときに成長を感じました。


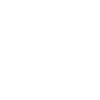


作品が大きいかつ、一回り大きな作品の中に入れて焼くので重さが2倍になり、
その作業や管理などに苦労しました。
また、5、6回も作り直したのでその点も苦労しました。
作品が大きいかつ、一回り大きな作品の中に入れて焼くので重さが2倍になり、その作業や管理などに苦労しました。
また、5、6回も作り直したのでその点も苦労しました。




大学4年間という短い時間の中で何かを完成させることが難しいので、
ここがスタート地点や分岐点だと思って、
今自分のできることをやることが大切だと思います。
大学4年間という短い時間の中で何かを完成させることが難しいので、ここがスタート地点や分岐点だと思って、今自分のできることをやることが大切だと思います。