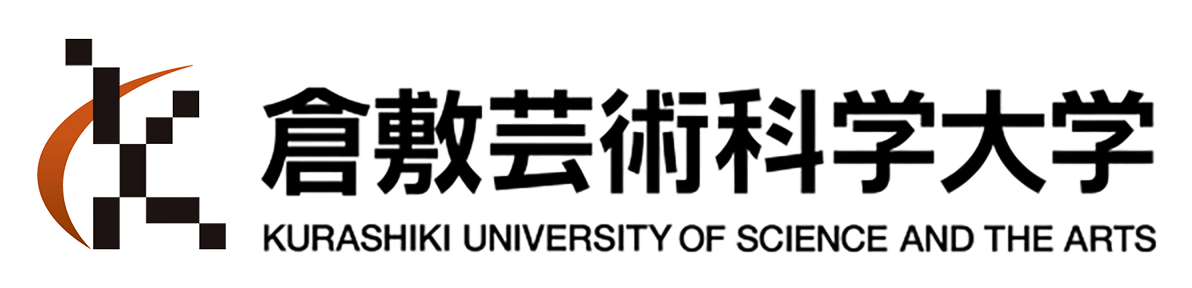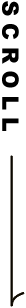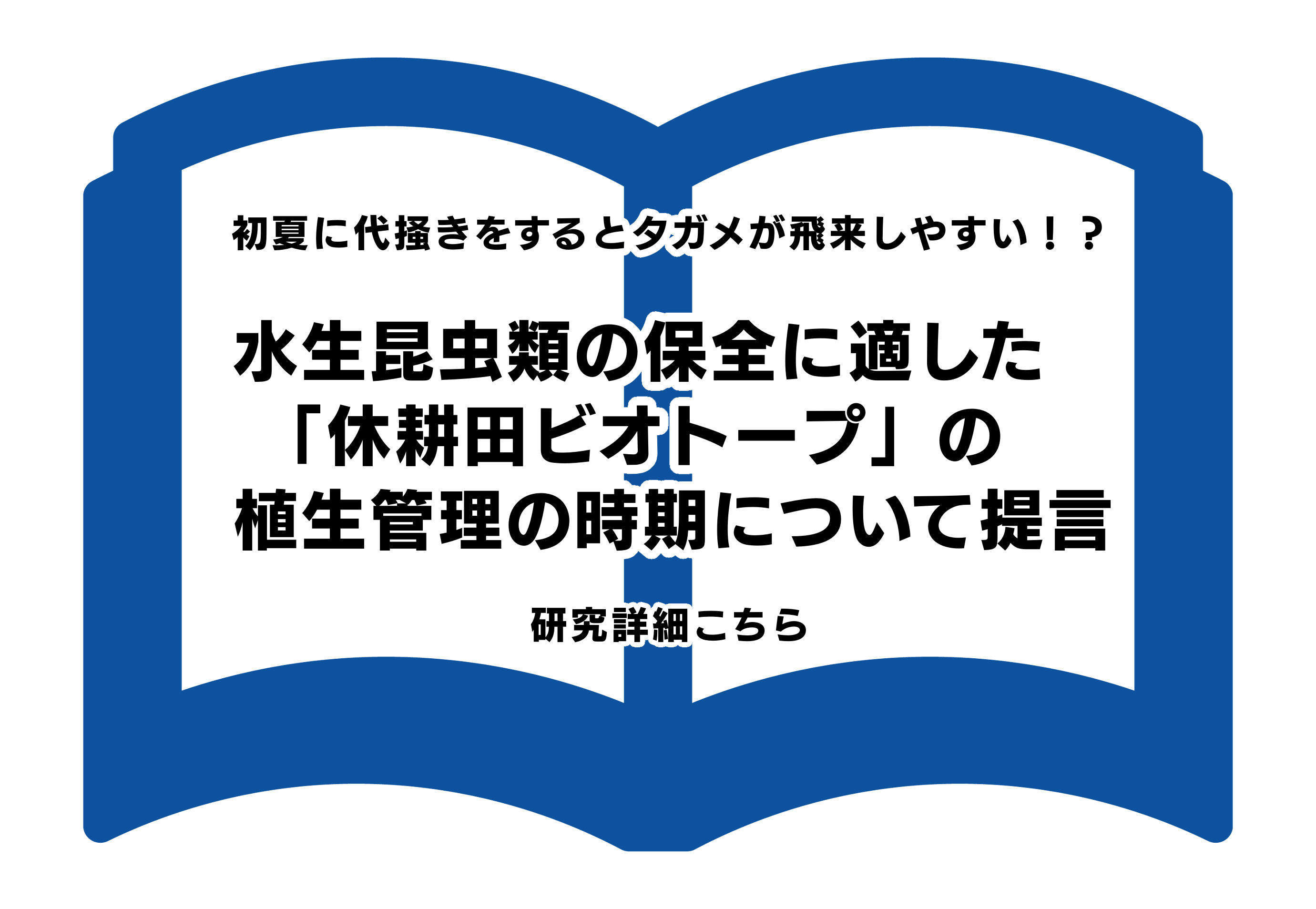アーカイブ
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2025.08.27
教育・研究Science
初夏に代掻きをするとタガメが飛来しやすい!?/環境生命科学科渡辺先生が国際誌『Hydrobiologia』に論文掲載
環境生命科学科の渡辺先生と株式会社ウエスコの久保星氏、長崎大学大学院博士後期課程の福岡太一氏、東北大学大学院の高橋真司技術専門職員、兵庫県立大学大学院の佐川志朗教授、長崎大学の大庭伸也准教授らの研究グループの論文が国際誌『Hydrobiologia』に掲載されました。
研究グループは休耕田ビオトープ(以下、ビオトープ)において、初夏に代掻きをして開放水面を創出すると、タガメなど一部の水生昆虫類の個体数が増加することを野外操作実験により明らかにしました。
広報ちゃんによる研究解説
みなさん、「生物多様性」って聞いたことありますか?
これは、いろんな種類の生き物が共に生きていることを意味します。生物多様性が高いと、生き物たちがバランスよく支え合って暮らせるので、人間にとっても安全で安心な環境が保たれます。例えば、昆虫が花粉を運んでくれるから作物が育つし、微生物が土をきれいにしてくれるから農業ができるんです。
でも今、日本では農業をやめる人が増えて、耕作放棄地(使われなくなった田んぼ) がどんどん増えています。そのまま放っておくと草や木が生えて、もともと田んぼにすんでいた水生昆虫やカエル、魚たちが住めなくなってしまいます。
そこで登場するのが 「ビオトープ」 です。
これは、もともと人が作った田んぼや土地を、水をためて池みたいにして、生き物がすめる環境を復活させた場所のことです。自然の小さな楽園って感じですね。
さらに、研究でポイントになったのが 「代掻き(しろかき)」 です。
これは田植え前に田んぼの土をかき混ぜて平らにする作業のこと。水草が生えすぎないようにする効果があります。水草が多すぎると水面がふさがれて、タガメみたいな水生昆虫は「ここは水辺じゃない!」と勘違いして飛んできてくれないんです。
倉敷芸術科学大学の渡辺先生を中心とした研究チームが実際に兵庫県で実験したところ、
代掻きをしなかったビオトープ → 水草が増えすぎて一部の昆虫の数が少なかった
代掻きをしたビオトープ → 水草が適度に減って、水田と同じくらいの数の昆虫が来た
という結果になりました。特にタガメに代表される初夏に繁殖を行う昆虫はビオトープの方が隠れる場所が多く、むしろよく育ったそうです。
これがどう役に立つの?
実はタガメなどの水生昆虫は、生態系のバランスを保つ大事な存在。彼らが生きられる環境は、人間にとっても安全で豊かな自然の証拠なんです。
さらに、この研究は環境省の「自然共生サイト」にも役立てられる予定で、地域の自然保護や教育活動にもつながります。
つまり、「使われなくなった田んぼでも、工夫して管理すれば生物多様性を守れる」
ということが証明されたんです。